寒さの中にも、天気の日は日差しが強くなり
春を感じるこの頃です。
春は終りと始まり、出会いと別れ、
さまざまな思いが錯綜する季節ですが、
すべて前向きに捉え、すべてを始まりに変える
力のある季節でもありますね。
動物園にも3月に入りシマフクロウ、レッサーパンダ、
ユキヒョウが新たに来園しました。
新たな環境での生活が始まります。
レッサーパンダは、人なつっこいというわけではなくて
警戒心がとても弱い動物で
新たな環境や飼育係との関係も
トラブルなく築ける個体が多い種です。
新入りのメス栃(とち)は新たな環境への適応という点では
来園して輸送箱から出た瞬間から、
新たな環境の探索を始め、自分たち(飼育係)はもとより
隣の部屋の向かえ入れる側のレッサーパンダにも目もくれることなく
我が物顔で新居を闊歩ていました。
次の日に新たなペアーを組むノノと同居させたのですが、
栃の方が我が物顔でノノの方が警戒していました。
さらに翌日に放飼場に出したのですが、
吊り橋も躊躇することなく渡りました。
そして6日目吊り橋を渡った先の木の側の囲いを乗り越え
園路を歩いていました。
積雪が原因だったので園路に出る原因は除去できたのですが、
目撃談によると、来園者が周りを取り囲む中
平然と園路を歩いていたようです。
ペットと違い野生種の動物は
他種との物理的な距離感、心理的な距離感を
絶妙なバランスで持っています。
他種を信頼することはないけど存在は認める、
食べる食べられる関係にある種が
空間を共有できる素晴らしい能力です。
旭山はその距離感を展示手法にも
日常の飼育にも取り入れて大切にしているのですが、
栃の距離感には戸惑わされます。
エサを持って寝室に入った時も
初対面なのに足にしがみつきよじ登ってきました。
エサの与え方種類が違うのにすぐに食べました。
飼育環境に関しては、
その動物が持つ能力を発揮できることが心理的に優位に働き
伸び伸びと過ごせ、見られているのではなく
見ている側の立場になれると考えているのですが、
裏を返すと人のいる側の環境は
動物が不安あるいは劣位になることを意味します。
もし優位、劣位さえ感じないのだとしたら
どのような行動に出るのか予測できません。
栃の生まれ育った環境の中での距離感は
旭山が持つ距離感と大分違います。
家ネコでもこうも無防備ではないだろうと思われるくらい、
距離感がゼロに近いのです。
さてこれからどうなるやら…
栃のあまりに近い距離感に一番悩まされるのは飼育担当者です。
胃潰瘍にならなければいいけどと心配になったりもしますが、
栃が元気ならばそれも仕方ないか、なんて思ったりもします。
後日談 この原稿は3月に書いたものです。
栃はノノとの交尾もし、
放飼場の外の世界への興味も無くなったようです。
今ではすっかり旭山の一員となりました。
春を感じるこの頃です。
春は終りと始まり、出会いと別れ、
さまざまな思いが錯綜する季節ですが、
すべて前向きに捉え、すべてを始まりに変える
力のある季節でもありますね。
動物園にも3月に入りシマフクロウ、レッサーパンダ、
ユキヒョウが新たに来園しました。
新たな環境での生活が始まります。
レッサーパンダは、人なつっこいというわけではなくて
警戒心がとても弱い動物で
新たな環境や飼育係との関係も
トラブルなく築ける個体が多い種です。
新入りのメス栃(とち)は新たな環境への適応という点では
来園して輸送箱から出た瞬間から、
新たな環境の探索を始め、自分たち(飼育係)はもとより
隣の部屋の向かえ入れる側のレッサーパンダにも目もくれることなく
我が物顔で新居を闊歩ていました。
次の日に新たなペアーを組むノノと同居させたのですが、
栃の方が我が物顔でノノの方が警戒していました。
さらに翌日に放飼場に出したのですが、
吊り橋も躊躇することなく渡りました。
そして6日目吊り橋を渡った先の木の側の囲いを乗り越え
園路を歩いていました。
積雪が原因だったので園路に出る原因は除去できたのですが、
目撃談によると、来園者が周りを取り囲む中
平然と園路を歩いていたようです。
ペットと違い野生種の動物は
他種との物理的な距離感、心理的な距離感を
絶妙なバランスで持っています。
他種を信頼することはないけど存在は認める、
食べる食べられる関係にある種が
空間を共有できる素晴らしい能力です。
旭山はその距離感を展示手法にも
日常の飼育にも取り入れて大切にしているのですが、
栃の距離感には戸惑わされます。
エサを持って寝室に入った時も
初対面なのに足にしがみつきよじ登ってきました。
エサの与え方種類が違うのにすぐに食べました。
飼育環境に関しては、
その動物が持つ能力を発揮できることが心理的に優位に働き
伸び伸びと過ごせ、見られているのではなく
見ている側の立場になれると考えているのですが、
裏を返すと人のいる側の環境は
動物が不安あるいは劣位になることを意味します。
もし優位、劣位さえ感じないのだとしたら
どのような行動に出るのか予測できません。
栃の生まれ育った環境の中での距離感は
旭山が持つ距離感と大分違います。
家ネコでもこうも無防備ではないだろうと思われるくらい、
距離感がゼロに近いのです。
さてこれからどうなるやら…
栃のあまりに近い距離感に一番悩まされるのは飼育担当者です。
胃潰瘍にならなければいいけどと心配になったりもしますが、
栃が元気ならばそれも仕方ないか、なんて思ったりもします。
後日談 この原稿は3月に書いたものです。
栃はノノとの交尾もし、
放飼場の外の世界への興味も無くなったようです。
今ではすっかり旭山の一員となりました。
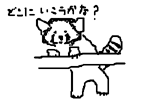 |
| レッサーパンダの栃(トチ)(ゲン画伯) |

