この日記は旭川市の「市民広報」に「動物園からの手紙」として毎月掲載されているものの、ほぼ原文です。なにぶん、原文なので不適当表現や言いまわしがあると思いますが、お許しを・・・。番外編も要注目です。ゲンちゃん画伯が書いた絵も楽しみながら、読んでみて下さい。
2009年5月30日土曜日
2009年4月30日木曜日
悪者は誰? (平成21年4月)
今年も例年になく早い雪解けでした。
4月の中旬まで雪割りに汗を流していたのがうそのようです。
流氷も早々と沖に姿を消し、ゴマフアザラシたちが心配です。
流氷の上で生まれたゴマフアザラシの赤ちゃんは、約3週間で離乳します。
離乳した子はたどたどしい泳ぎで、
自力で食べ物を確保しなければいけません。
水深の深い沖合いの海では食べ物を採ることが出来ません。
4月は越冬をしに日本に渡ってきていた渡り鳥が
繁殖のために北に向かう季節です。
オオハクチョウも群れでシベリアを目指します。
北海道では昨年5月に
野付半島とサロマ湖で死亡していたオオハクチョウ各1羽から
高病原性鳥インフルエンザの感染が証明されました。
その後の水鳥類の糞便を中心にした疫学調査からは、
ウイルスはみつからず、オオハクチョウを含め鳥類の大量死や、
罹患個体(病気にかかっている個体)も見つかりませんでした。
オオハクチョウからの高病原性鳥インフルエンザの発生を受け、
昨年の秋から水鳥類への餌付け自粛が広がりました。
それに伴いハクチョウたちの行動にも当然変化が現れ始めました。
人とのかかわりが
より自然な関係に向かう出発点となればいいと考えています。
ところが、3月7日付けの新聞に
「タンチョウ、鳥インフル感染の危機 阿寒 餌場にオオハクチョウ」
という記事が載っていました。
高病原性鳥インフルエンザと鳥インフルエンザを区別していないという
根本的な誤りもあるのですが、
タンチョウの餌場にオオハクチョウが現れるようになったので、
追い払いを考えなければいけないといった趣旨の内容でした。
あまりに短絡的で危険な記事だと思います。
平成6年にエキノコックス症発生で閉園した際の
キタキツネに対する反応を思い出します。
それまでマスコット扱いで可愛がり餌付けをし、
人の生活圏に招きいれておきながら「怖い」となると
手のひらを返すように悪者扱いになりました。
ましてオオハクチョウは昨年「単発的」に発生が確認されただけで、
オオハクチョウも被害者である可能性が高いのです。
タンチョウは過去に絶滅のふちから冬場の餌付けにより個体数を増やし
絶滅を回避した経過があります。
生息環境が悪化し続ける中で餌付けにより個体数が増え、
近年ではタンチョウによる農作物の被害も問題になり始めています。
タンチョウも「悪者」になる可能性を秘めています。
良くも悪くも人が深く係ることが問題の発生源であることを
自覚しなければいけないのではないでしょうか?
もっと言えば人の生活とはそういう一面を持っていることを知ることから
問題解決を考えないといけないのではないでしょうか?
オオハクチョウは悪者ではないのです。
4月の中旬まで雪割りに汗を流していたのがうそのようです。
流氷も早々と沖に姿を消し、ゴマフアザラシたちが心配です。
流氷の上で生まれたゴマフアザラシの赤ちゃんは、約3週間で離乳します。
離乳した子はたどたどしい泳ぎで、
自力で食べ物を確保しなければいけません。
水深の深い沖合いの海では食べ物を採ることが出来ません。
4月は越冬をしに日本に渡ってきていた渡り鳥が
繁殖のために北に向かう季節です。
オオハクチョウも群れでシベリアを目指します。
北海道では昨年5月に
野付半島とサロマ湖で死亡していたオオハクチョウ各1羽から
高病原性鳥インフルエンザの感染が証明されました。
その後の水鳥類の糞便を中心にした疫学調査からは、
ウイルスはみつからず、オオハクチョウを含め鳥類の大量死や、
罹患個体(病気にかかっている個体)も見つかりませんでした。
オオハクチョウからの高病原性鳥インフルエンザの発生を受け、
昨年の秋から水鳥類への餌付け自粛が広がりました。
それに伴いハクチョウたちの行動にも当然変化が現れ始めました。
人とのかかわりが
より自然な関係に向かう出発点となればいいと考えています。
ところが、3月7日付けの新聞に
「タンチョウ、鳥インフル感染の危機 阿寒 餌場にオオハクチョウ」
という記事が載っていました。
高病原性鳥インフルエンザと鳥インフルエンザを区別していないという
根本的な誤りもあるのですが、
タンチョウの餌場にオオハクチョウが現れるようになったので、
追い払いを考えなければいけないといった趣旨の内容でした。
あまりに短絡的で危険な記事だと思います。
平成6年にエキノコックス症発生で閉園した際の
キタキツネに対する反応を思い出します。
それまでマスコット扱いで可愛がり餌付けをし、
人の生活圏に招きいれておきながら「怖い」となると
手のひらを返すように悪者扱いになりました。
ましてオオハクチョウは昨年「単発的」に発生が確認されただけで、
オオハクチョウも被害者である可能性が高いのです。
タンチョウは過去に絶滅のふちから冬場の餌付けにより個体数を増やし
絶滅を回避した経過があります。
生息環境が悪化し続ける中で餌付けにより個体数が増え、
近年ではタンチョウによる農作物の被害も問題になり始めています。
タンチョウも「悪者」になる可能性を秘めています。
良くも悪くも人が深く係ることが問題の発生源であることを
自覚しなければいけないのではないでしょうか?
もっと言えば人の生活とはそういう一面を持っていることを知ることから
問題解決を考えないといけないのではないでしょうか?
オオハクチョウは悪者ではないのです。
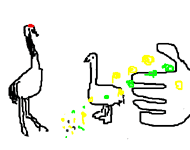 |
| 一方的な愛情!?(ゲンチャン画伯) |
2009年2月28日土曜日
流氷ひろば (平成21年2月)
さて,今は映画公開前の取材ラッシュです
(原稿を書いたのが1月18日なので…)。
対応に大わらわなのですが,旭川の先行上映,
そして全国上映と順調な船出を迎えられたらいいなと願っています。
それにしても今年の冬はつかみ所がありませんね。
そんなに寒いわけでもなく,
雪も全か無みたいな降り方をするし…
あざらし館念願の流氷作戦も新戦略をたてて挑んでいますが,
はたしてどうなりますか?
昨年はプールの一部を仕切り止水域として結氷できたのですが,
仕切をはずすと水温が高くなり,氷と水面の間に空気層ができてしまい
今ひとつ臨場感に欠けてしまいました。
今シーズンは循環ろ過の宿命である
高水温をいかに下げるかに挑んでいます。
ちょっとマニアックな話になるのですが,
あざらし館のプールの水は,循環ろ過をして透明度を保っています。
アザラシは水中で糞を大量にするので,
ろ過能力はぺんぎん館などよりも高能力です。
プールの水約250トンを一時間でろ過する能力があります。
ちょっと乱暴な言い方ですが一日に24回
水を入れ替えていることになります。
さて問題はろ過器のある機械室は
プラス5度以上に保たなければいけません。
さらに来園者のはいる館内は十数度になるようにしています。
つまり保温している状態なのです。
あざらし館のろ過はちょっと特殊で,
透明度を維持する物理ろ過槽の他に,
巨大な生物ろ過槽があります。
これは透明度を維持するためではなく,
水質を魚がすめるようにするためのものです。
水質の検査を継続する中で,
この生物ろ過はそれほど有効に働いていないことが分かっていたので,
このろ過槽のろ剤を入れ替えて物理ろ過槽にしました。
そしてろ過流量を下げて,
プールの水がより長く外気温にさらされるようにしました。
さらに夜間ろ過を止める試みも始めました。
オープン以来24時間ろ過は稼働していました。
来園者が不快に思うくらいに水が濁るのが怖くて
ろ過を止める試みはしていませんでした。
そこで正月の閉園期間中に夕方からろ過を止める実験をしました。
朝,ろ過を始めると開園の時間までには水の濁りは許容範囲まで
回復することが確かめられました。
現在まで(1月18日)この方法を継続することで,
最低気温が下がらない中で,
水温は徐々に下がり3度台まで下がって来ています。
躯体(くたい)のコンクリートも冷えてきたようです。
ここで一気に大量の雪を投入して表面が凍れば
流氷作戦に明かりが差し込みます。
明日,第一弾の雪大量投入作戦を決行します。
担当者も頑張っています。
どんな結果になるか楽しみです。
この手紙が届く頃には
もしかしたら水中から流氷の底を見上げる景色が…
そんなに甘くはないかな…
(無事に流氷広場が完成しました。
あざらし館のコンセプト「流氷と共に生きるアザラシ」が実現できました!)
(原稿を書いたのが1月18日なので…)。
対応に大わらわなのですが,旭川の先行上映,
そして全国上映と順調な船出を迎えられたらいいなと願っています。
それにしても今年の冬はつかみ所がありませんね。
そんなに寒いわけでもなく,
雪も全か無みたいな降り方をするし…
あざらし館念願の流氷作戦も新戦略をたてて挑んでいますが,
はたしてどうなりますか?
昨年はプールの一部を仕切り止水域として結氷できたのですが,
仕切をはずすと水温が高くなり,氷と水面の間に空気層ができてしまい
今ひとつ臨場感に欠けてしまいました。
今シーズンは循環ろ過の宿命である
高水温をいかに下げるかに挑んでいます。
ちょっとマニアックな話になるのですが,
あざらし館のプールの水は,循環ろ過をして透明度を保っています。
アザラシは水中で糞を大量にするので,
ろ過能力はぺんぎん館などよりも高能力です。
プールの水約250トンを一時間でろ過する能力があります。
ちょっと乱暴な言い方ですが一日に24回
水を入れ替えていることになります。
さて問題はろ過器のある機械室は
プラス5度以上に保たなければいけません。
さらに来園者のはいる館内は十数度になるようにしています。
つまり保温している状態なのです。
あざらし館のろ過はちょっと特殊で,
透明度を維持する物理ろ過槽の他に,
巨大な生物ろ過槽があります。
これは透明度を維持するためではなく,
水質を魚がすめるようにするためのものです。
水質の検査を継続する中で,
この生物ろ過はそれほど有効に働いていないことが分かっていたので,
このろ過槽のろ剤を入れ替えて物理ろ過槽にしました。
そしてろ過流量を下げて,
プールの水がより長く外気温にさらされるようにしました。
さらに夜間ろ過を止める試みも始めました。
オープン以来24時間ろ過は稼働していました。
来園者が不快に思うくらいに水が濁るのが怖くて
ろ過を止める試みはしていませんでした。
そこで正月の閉園期間中に夕方からろ過を止める実験をしました。
朝,ろ過を始めると開園の時間までには水の濁りは許容範囲まで
回復することが確かめられました。
現在まで(1月18日)この方法を継続することで,
最低気温が下がらない中で,
水温は徐々に下がり3度台まで下がって来ています。
躯体(くたい)のコンクリートも冷えてきたようです。
ここで一気に大量の雪を投入して表面が凍れば
流氷作戦に明かりが差し込みます。
明日,第一弾の雪大量投入作戦を決行します。
担当者も頑張っています。
どんな結果になるか楽しみです。
この手紙が届く頃には
もしかしたら水中から流氷の底を見上げる景色が…
そんなに甘くはないかな…
(無事に流氷広場が完成しました。
あざらし館のコンセプト「流氷と共に生きるアザラシ」が実現できました!)
 |
| 流氷ひろばのゴマフアザラシ(ゲンチャン画伯) |
登録:
投稿 (Atom)
